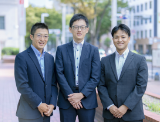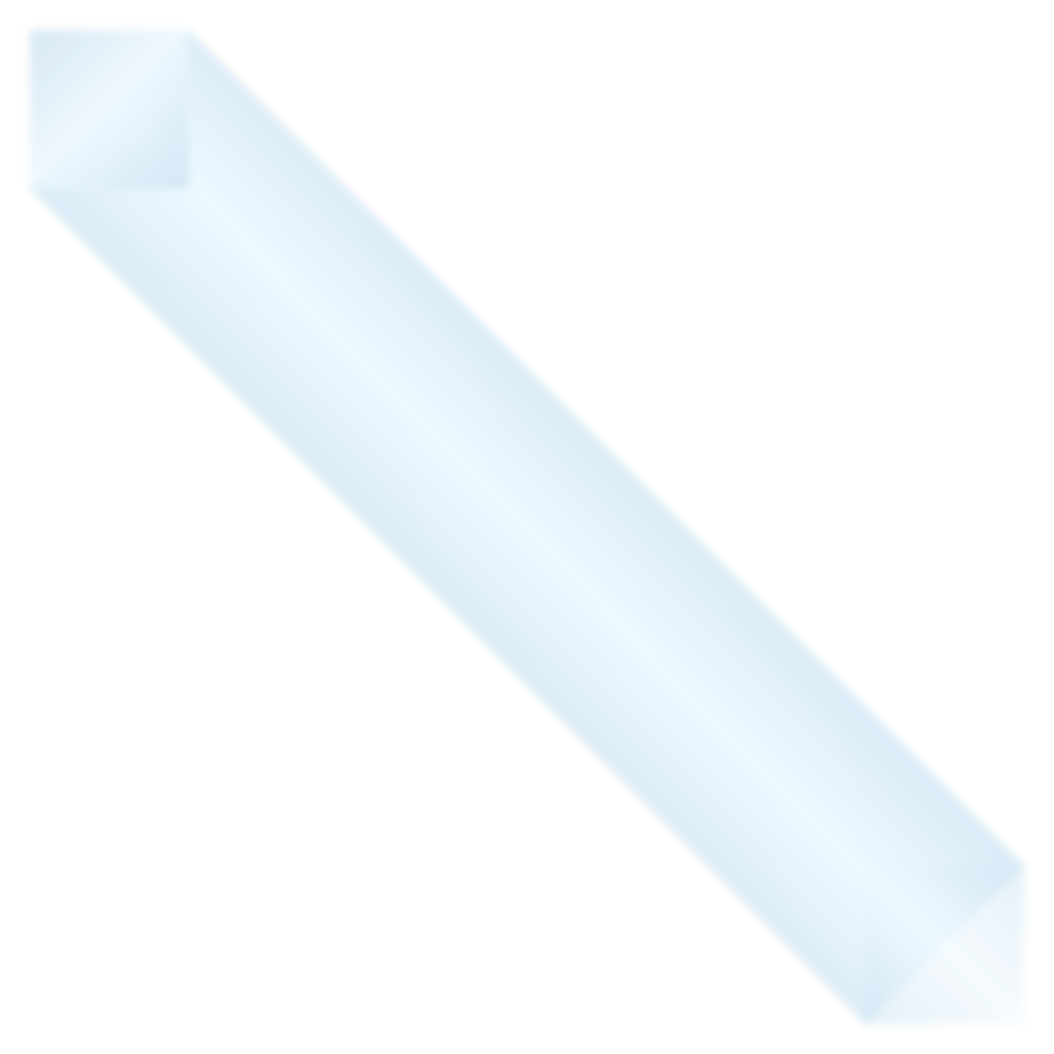

自社開発パッケージ「SMART SHOMU®」で、国内全域への事業展開を着々と進行
NTTデータ東海 × 公共分野
東海地方の県や市町村などの自治体向けに、システム開発を長年にわたって取り組んできたNTTデータ東海。その過程で獲得した自治体業務に関する知識と開発ノウハウは膨大であり、他社をリードする競争力につながっています。そうした中で自治体の庶務業務に関する知見を集約し、パッケージ化による開発効率の向上を図ったのが、自治体の多彩な庶務業務をサポートする「SMART SHOMU®」です。すでに市場展開し、全国の自治体でトップクラスのシェア獲得に至りました。この優れたパッケージを名古屋からどのように全国展開しているか、その戦略を見ていきましょう。
-
M.K.
公共分野 開発担当 / 課長
2006年入社「SMART SHOMU®」の名付け親であり、自治体庶務システムのパッケージ化を先導した一人。入社2年目より、さまざまな自治体への庶務事務システムのスクラッチ開発に関わってきた。現在はPMとしてシェア拡大を図っている。

-
S.Y.
公共分野 開発担当 / 課長代理
2016年入社前職はNTTデータ東海の協力会社の一員。その後当社に入社し、K県庁およびT市での「SMART SHOMU®」の運用保守業務に従事することに。「SMART SHOMU®」を扱うNTTデータグループ各社からの問い合わせ窓口としても活躍。

-
R.Y.
公共分野 開発担当 / 主任
2017年入社入社半年後に、Y市教育委員会における「SMART SHOMU®」導入案件で改修業務に従事。その後の3年間は運用保守業務を担い、現在は再度改修業務に戻って仕様調整から試験、プロジェクトの進捗管理等を手掛けている。

※掲載内容は取材当時のものです(2024年10月)
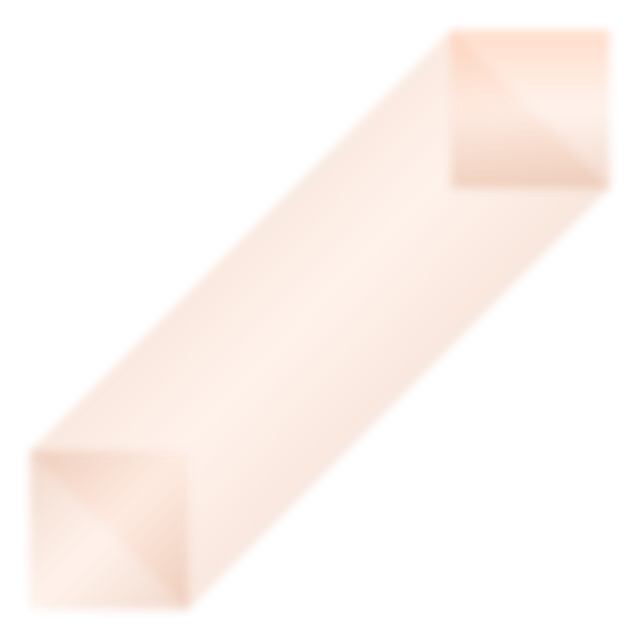
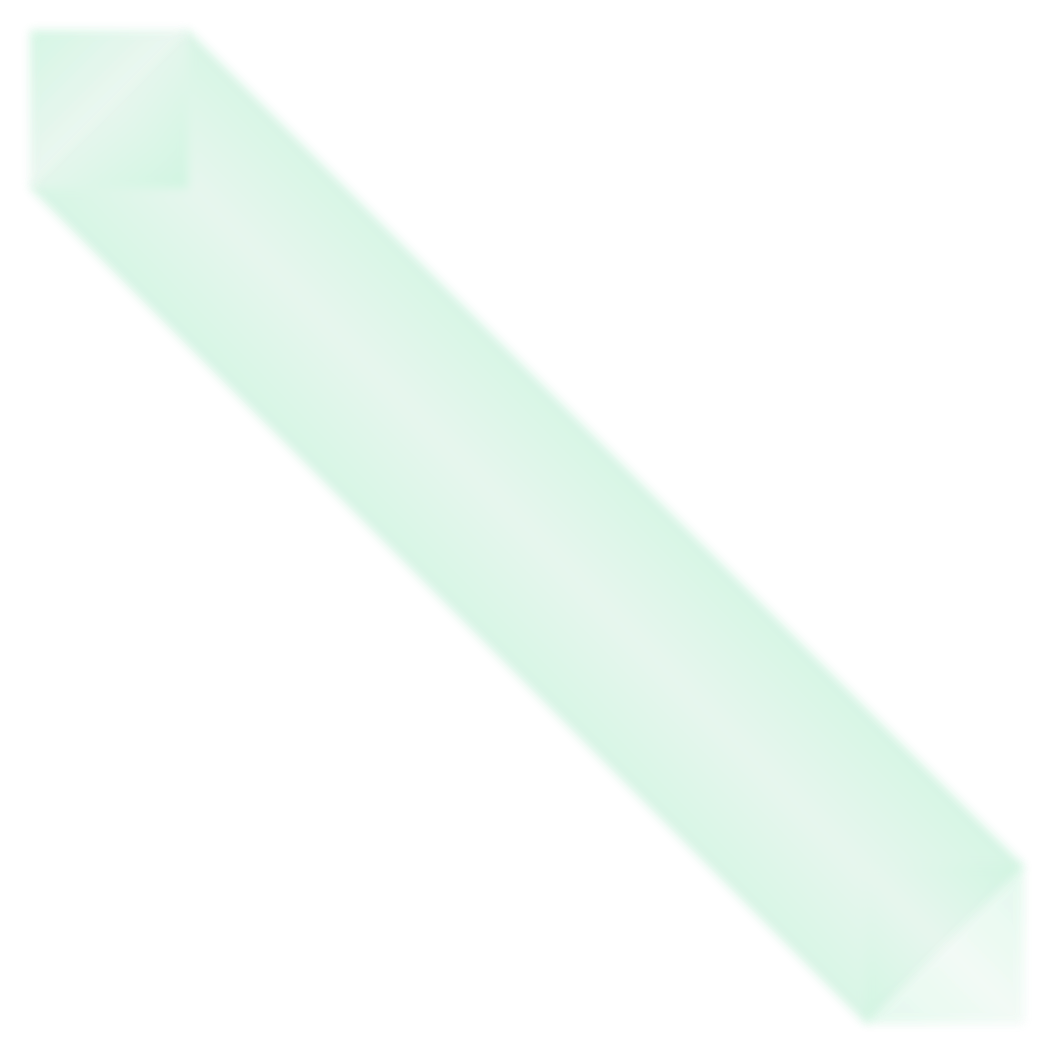
[ #1 ]プロジェクトのミッション
競合に先行するためのパッケージ化
-
 M.K.
M.K.私は2006年の入社の翌年から、自治体向けの庶務事務システムのスクラッチ開発に携わりました。そして、東海地方の数々の自治体への導入実績を重ね、庶務事務の業務知識やそのバックエンドのシステム化、さらにはユーザー入力の電子化に関する技術を蓄積できたことで、パッケージ化する機運が公共分野部内で高まってきました。限られたメンバーでも対応案件を拡大できる開発効率の向上、導入期間の短縮、それらに伴うコスト競争力の獲得など、数々のメリットが考えられたからです。スクラッチでの受託案件と並行して開発したために、プロダクト化には数年かかりましたが、2015年頃にパッケージ化に至りました。「SMART SHOMU®」の名付け親は実は私で、商標登録やパンフレット制作にも携わっています。
-
 S.Y.
S.Y.「SMART SHOMU®」の大規模自治体への最初の導入案件が、K県庁でした。アプローチを開始したのが2014年頃です。私はこの案件には要件定義後の開発業務から入りました。K県は職員数5万人規模の大型自治体であり、その職員の全員が利用するシステムであることから開発には力が入りました。
-
 R.Y.
R.Y.その翌年の2015年に、同じK県のY市の教育委員会にも「SMART SHOMU®」の導入が決まりました。上司であるM.K.が業務リーダーを務め、コンペに勝って受注したのです。価格と機能の総合評価点で上回ったと聞いています。K県庁の受注案件と直接の関係はありませんが、この案件の開発を担当することになった私は、S.Y.と情報を共有しながらプロジェクトを進められました。
-
 M.K.
M.K.以上の2案件は、「SMART SHOMU®」の現在の躍進の起点となったプロジェクトです。いずれも2017年にサービスを開始しました。私はPMを務め、現在も我々による運用・保守、さらには追加機能開発が続いています。

[ #2 ]課題解決のポイント
複雑な要件を取り込みつつカスタマイズ性も持たせる
-
 M.K.
M.K.自治体の職員が行う各種申請や届出作業を電子化した「SMART SHOMU®」ですが、自治体ごとに異なる要件に対応するために、ガチガチに仕様を固めてはおらず、カスタマイズ面で自由度が大きいのも特徴です。実際、各自治体には業務の遂行上で独自の細かい制度が存在し、そのシステム化は容易ではありません。また、法改正に伴ってシステムを柔軟にアップデートしていく必要もあります。最近の例で言えば、年末調整や児童手当に関する制度改正がありました。このようにパッケージと言えども、自治体の庶務業務システムには柔軟性や拡張性が求められるのです。
-
 S.Y.
S.Y.自治体ごとに要求されるまったく異なる複雑な要件をカバーしなければならないケースも多く、実は個別対応が前提のスクラッチで開発した方が都合の良い面もあるのです。ですが、我々は自治体庶務業務に関する膨大なノウハウを活かし、庶務事務システムのパッケージ化のメリットを追求しました。
-
 R.Y.
R.Y.リリースした最初の頃のコンペ相手のほとんどは、スクラッチ開発を提案していました。でも「SMART SHOMU®」の評価が高まり、シェアを拡大し始め、パッケージのメリットが自治体に伝わり始めると、最近はパッケージ化で追随してくる競合も出てきました。ただ、まだまだ「SMART SHOMU®」の先進性は高く、アドバンテージは大きいと感じています。

[ #3 ]NTTデータ東海のValues
販売チャネルを拡大し名古屋から全国へ
-
 S.Y.
S.Y.私はK県庁の担当を引き続き行いながら、導入済みであるT市での保守も担っています。また、NTTデータグループであるNTTデータアイ社が「SMART SHOMU®」を某大規模自治体の総務局に提供していますが、開発元のエンジニアとして問い合わせに対応することも業務の一環となっています。
-
 R.Y.
R.Y.私もY市教育委員会での定期改修が一段落している時は、他の導入案件をサポートすることが多いですね。ただ、Y市もそうですが、先方に訪問する必要があるのは提案時や導入初期の頃のみです。リリース後は現地の協力会社と連携しながら、名古屋で全国の自治体の開発支援が可能になっています。
-
 M.K.
M.K.「SMART SHOMU®」はNTTデータ東海が開発しましたが、優れたパッケージであるだけに、営業 / マーケティングに関してはNTTデータグループ各社や地域会社も行っています。例えばNTTデータ北海道、NTTデータ四国、NTTデータ九州がそれぞれの担当エリアの自治体に、NTTデータ東海の協力のもと、導入を行いました。我々自身もK県庁のみならず、G県庁やS県庁に導入を進めています。また、NTTグループ外の企業とも組んでS県庁への導入も進んでいます。

[ #4 ]成果とやりがい
12県庁に導入し、シェアNo.1を獲得
-
 S.Y.
S.Y.自社のプロダクトなので、案件ごとに仕様の検討から製造まで自分たちが主導できるやりがいは大きいです。お客様から対応が難しい要望を受けた際でも、ヒアリングを重ね、要望の中身をしっかり確認し、「SMART SHOMU®」で実現できた時は、大きな達成感があります。
-
 R.Y.
R.Y.「SMART SHOMU®」を通してNTTデータ東海に対する信頼や評価が高まっているのを感じられます。運用を開始してから感謝の言葉をいただくことも少なくありません。
-
 M.K.
M.K.「SMART SHOMU®」は現在では全国の12県庁に導入済みであり、県庁におけるシェアはNo.1です。今後は他の都道府県庁ならびに政令指定都市、中核都市へと導入自治体を拡大していくことを目指しています。自分たちのプロダクトを成長させる醍醐味は大きいですね。

[ #5 ]展望
クロス・バリューズの理念でさらに優れたパッケージに
-
 M.K.
M.K.おかげさまで「SMART SHOMU®」は我々のみならず、NTTデータグループも取り扱うケースが増え続け、このパッケージに関わるSEや営業はかなりの人数になっています。ただ、横のつながりや情報の共有化は十分に進んでいるとは言えません。我々は開発元として、「SMART SHOMU®」を多くの自治体に広めていくメンバーに、十分な情報やノウハウを提供したいと考えています。それにはグループ企業の垣根を超えたメンバーの交流を積極的に図る必要があるでしょう。例えば喫緊の課題として、保守作業の効率化が挙げられますが、保守作業を統合し、ノウハウを共有することで解決に導けるはずです。NTTデータ東海は新しいビジョンとして、多くのメンバーやその価値観がクロスして新しい価値を創出していこうとする「クロス・バリューズ」を掲げましたが、まさにこの理念で「SMART SHOMU®」を成長させていきたいのです。